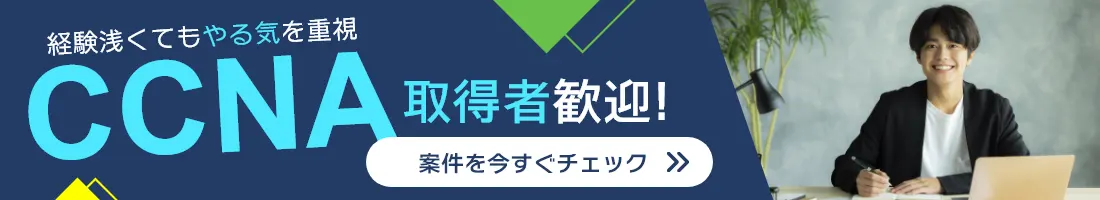テスト環境とは何か?テストの種類6つやテスト環境におけるテストの流れなど紹介

テスト環境とは何か?

システム開発におけるテストとは、システムが正しく動作するかどうかの検証作業を行うことです。
テストはシステムの不具合を取り除いたり、仕様どおりの動きになっていることを確認したりする非常に重要な工程です。テストで不具合が見つかった場合は修正して再度テストを行い、最終的に不具合が見つからなくなるまで作業を繰り返します。
なぜテスト環境が必要なのか
テストを行わずににただ単に動くようになっただけのシステムには、多くのバグが含まれている可能性があります。
人が手作業でコーディングしている以上、まったくバグを含まないシステムを開発することは難しいですが、テストを行うことによってできるだけバクを取り除いてシステムのクオリティを上げることができます。
そのため、本番に近いテスト環境でさまざまなテストを行い、正常に稼働することを確かめる必要があります。
テストの種類6つ

実際に開発されたシステムのテストを行う場合、どのような流れで行われるのでしょうか。ここではシステム開発におけるテストの流れ6ステップをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1:単体テスト
単体テストとは、システム単体で行われるテストです。別名「ユニットテスト」とも呼ばれるテストで、個別のプログラムの機能が正しく動作しているかどうかを検証します。
また、単体テストは早い段階で実施されるためバグの発見が容易で、この段階でできるだけバグを除去することでシステムの品質を高めることができます。
2:結合テスト
結合テストとは、複数のプログラムを連携させた際に正しく動作するかを検証するテストです。
結合テストは個別の単体テストが終了した段階で行うもので、個別のプログラムを実行した際には発生しないような想定外の動作などを見つけることができます。
3:総合テスト
システムテストとは、開発したシステム全体で正しく動作するかを検証するテストです。
別名「総合テスト」とも呼ばれるテストで、実際に使用する場合に仕様どおりに完成しているかを確認します。また、システムテストはできるだけ本番に近い環境で実施されます。
4:確認テスト
確認テストは、システム修正時に変更していない箇所に影響が出ていないかどうかを検証するテストです。修正箇所以外の場所で不具合が発生していないかを確認します。
機能修正を実施するシステム開発の際には必ず行われるテストです。
5:評価テスト
評価テストは、システムの操作性や脆弱性などを検証するテストです。
ハードウェアの故障やデータベースダウンを想定し、データベースとの接続を遮断するなどの方法で擬似的に障害を発生させて、障害発生時にもシステムが動作するかどうか、復旧手順によって復旧ができるかなどの検証も行います。
6:負荷テスト
負荷テストは、過負荷状態の際にシステムが問題なく動作することを検証するテストです。
多くのアクセスを一度に行うことで、実際にシステムが稼働した際の高負荷状態でも正常に動作できるかどうかを確認します。
具体的には、過負荷な状態で発生する競合条件や排他制御、メモリリークなどのバグを検出します。
テスト環境でテストする主要5項目

システム開発で実施されるテストにはさまざまな種類があり、テストの目的に合わせて「確認テスト」や「評価テスト」、「負荷テスト」などの種類にわかれます。
ここではシステム開発における5つのテストについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
1:求められている機能が正しく動作するか
システムの性能要件に対して開発したシステムの処理能力が仕様を満たしていることを検証するテストとして、性能テストがあります。
システムのパフォーマンスを確認するもので、システムの時間効率や資源効率といった特定条件でのレスポンスタイムを測定し、その結果をベースに最適化やチューニングを実施します。
2:UIは使いやすいか
システムを使う側の操作性などを検証するテストとして、ユーザビリティテストがあります。
ユーザビリティテストでは、開発したシステムが使いやすいかどうか、見やすいかどうか、わかりやすいかどうかなどのユーザー目線での操作性についてチェックを実施します。
システム開発時にユーザビリティテストを実行することで、システムを利用したユーザーの満足度を向上することが可能です。
3:セキュリティに問題はないか
セキュリティに関する機能を検証するテストとして、セキュリティテストがあります。
主に不特定多数のユーザーに利用されるようなシステムでは必須のテストとなっており、セキュリティ設計どおりの実装になっているかどうかや実際に不正アクセスを防止できているか、設計で漏れている脆弱性がないかどうかなどを確認します。
4:負荷をかけたときにどの程度安定動作するか
一定期間システムを連続稼働させてパフォーマンスを検証するテストとして、ロングランテストがあります。
連続稼働することによってシステムが停止しないかどうか、パフォーマンスが落ちないかどうかを確認します。ロングランテストによってシステムの稼働率や処理能力に問題がなく、信頼性があることを検証できます。
5:予期せぬエラー・バグの検証
システム修正時に変更していない箇所に影響が出ていないかどうかを検証するテストとして、リグレッションテストがあります。
別名「回帰テスト」とも呼ばれるもので、システムを修正したことにより、修正箇所以外の場所で不具合が発生していないかを確認します。修正を実施するシステム開発の際には必ず行われるテストです。
WordPressでのテスト環境の作り方4つ

WordPressは便利なWebサイト作成ツールで、テスト環境を作成できます。
テスト環境を作るためには「Local by Flywheel」を使用します。ここでは、WordPressでのテスト環境の作り方4つを紹介していきます。
1:「Local by Flywheel」を使用する
1つ目のテスト環境の作り方は「Local by Flywheel」を使用することです。
「Local by Flywheel」は、パソコン内のローカル環境で疑似的なWordPressを構築するツールで、本番の環境を想定したテスト環境を構築できます。
「Local by Flywheel」を使用して不具合を出しても、本番サイトに影響はないので、気兼ねなくテストとバグ修正ができます。
2:「Local by Flywheel」のインストールの仕方
2つ目は「Local by Flywheel」のインストールの仕方です。
「Local by Flywheel」はプラグインではないので、WordPressからではなく配布サイトからファイルをダウンロードして、インストールする必要があります。
配布サイトでダウンロードする際は、メールアドレスなどの項目を記入する必要があります。
3:インストール後はテスト環境の構築に入る
3つ目は、インストール後はテスト環境の構築に入ることです。
ファイルのインストールが完了したら、テスト用のドメイン名とサーバ設定してテスト環境の構築に入ります。
サーバは「Preferred」と「Custom」から選べ、PHPのバージョン、サーバの選択、MySQLのバージョンなどの設定を変更する際は「Custom」を選択する必要があります。
4:ユーザー名とパスワードを発行する
4つ目は、ユーザー名とパスワードを発行することです。
テスト環境を構築したら、ユーザー名とパスワードを発行してテスト環境を構築できます。その後、WordPressの管理画面に移動してサイトの編集をします。
設定したIDとパスワードは、他のテスト環境でも利用可能になるよう設定でき、複数のテストも簡単に構築できることでしょう。
テスト環境におけるテストの流れ5つ

運用テストは他の検証作業を全て終了し、本番稼働前にクライアントと一緒に行う最後のテストです。運用テストによって業務担当者もシステムの操作や運用のリハーサルを行います。
また、運用テスト環境で不具合が見つかった場合はすぐに改修作業を行います。ここではシステム開発における運用テストの流れをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1:テストの計画を作成
運用テストを行う場合は、まずはテスト計画書を作成する必要があります。運用テスト計画書には、どのようなテストを実施するかという概要や全体の方針などをまとめます。
具体的には、テストの目的や具体的な方法、スケジュールやテスト環境、合格基準などのテストを実施するために必要な情報をまとめて、クライアントの担当者やメンバーで共有します。
2:テストの工程を仕様書にまとめる
作成した運用テスト計画に基づいた運用テスト仕様書を作成します。仕様書にはテストのシナリオや具体的な内容、チェック項目などをまとめておき、テストデータの内容についても定義を行います。
3:可能な限り本番環境に近いテスト環境を構築
運用テスト計画に基づいて運用テスト環境の構築を行います。テスト環境は本番の稼働環境に近い環境を構築します。
また、実際の本番環境が利用できる場合はテスト環境ではなく本番環境にテストデータを作成してテストを行うこともあります。
4:仕様書に沿ったテスト作業
運用テスト仕様書に基づいて運用テストを実施します。プロジェクトメンバーやクライアントの業務担当者などのテスト実施者が実際に運用テストを行っていきます。
また、運用テストによって不具合や障害が見つかった場合には、障害管理票を作成して不具合が解消されるまで管理することになります。
5:テスト工程の自動化
テスト工程の自動化は、人の手でテストを行う際に発生するコストを削減でき、効率化に大きく貢献します。
また、テスト工程作業に余裕が生まれることで、問題が発生したテストの再検討や対処を実施することが可能であることやテスト環境での作業に人為的ミス解消にも効果を発揮します。
システム開発における環境の役割4つ
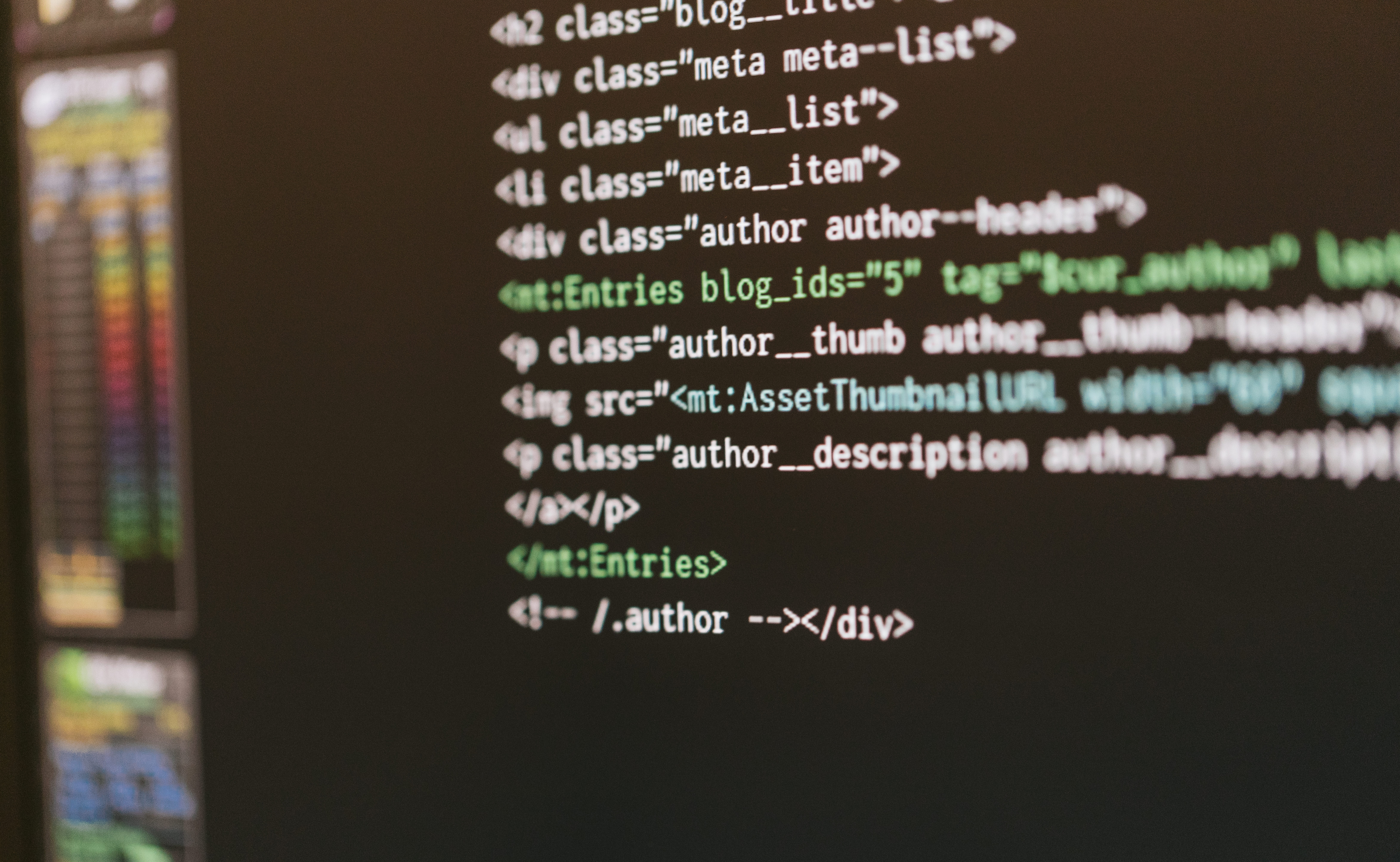
システム開発における環境の役割は4つあります。システム開発における開発環境には、開発を実施するためのベースとなる開発マシン環境や追加した機能の正常性を検証する環境、開発した製品のリリース後の実環境などがあります。
ここでは、それぞれの開発環境の役割について詳しく紹介していきます。
1:開発環境(ローカル環境)
開発環境(ローカル環境)とは、開発者がプログラム作成や検証で自由に使用できる環境のことです。
エラー処理のチエックを行う時には、実際と同じようにプログラムを壊して原因を追求したり、ハードウェアの電源をオフにして確かめます。
故意に故障を作り出したり、それを回復させるといった検証を行うための環境が開発環境です。
2:検証環境(テスト環境)
検証環境(テスト環境)とは、開発工程が完了した後に、リリースするプログラムの機能が正常に動作するか検証するための環境のことです。
一般的に、開発工程では、事前に開発テスト環境と検証テスト環境の2つを準備しておきます。
特に工程が多い開発の場合は、2つの工程を並行して実施しています。
発見した不具合をその時点ですぐ検証して、開発テスト環境でフィードバックするための環境が検証環境といえるでしょう。
3:ステージング環境
ステージング環境は、最終の本番環境と同じで不具合を取除いた後の機能部分のリリース前チェック環境です。
本番のテスト環境と同じ環境で、リリースと同じデータでチェックができます。新しい機能データと余分なデータなどを設定して影響度合いを検証することも可能です。
4:本番環境
別名商用環境とも呼ばれる本番環境は、文字通り製品リリース後の環境と同じ環境のことを指します。
最終的な動作の確認を行う際に使われる環境です。ユーザー視点で実際の挙動などを確認することができます。
テスト環境でテストすることで本番環境でのエラーを防ごう

システム開発では、開発されたシステムに含まれている不具合を除去したり、過負荷時に正常な動作ができるかどうかを確認したり、ユーザビリティを向上したりするためにさまざまな種類のテストを実施します。
そのため、テストはシステム開発と同様に重要な工程となっています。ぜひこの記事でご紹介したシステム開発におけるテストやテストの流れを参考に、システム開発を行う際に重要なテストについて理解を深めてみてはいかがでしょうか。
FEnetを運営しているネプラス株式会社はサービス開始から10年以上
『エンジニアの生涯価値の向上』をミッションに掲げ、
多くのインフラエンジニア・ネットワークエンジニアの就業を支援してきました。

ネプラス株式会社はこんな会社です
秋葉原オフィスにはネプラス株式会社をはじめグループのIT企業が集結!
数多くのエンジニアが集まります。

-
インフラ業界に特化

ネットワーク・サーバー・データベース等、ITインフラ業界に特化。Cisco Systemsプレミアパートナーをはじめ各種ベンダーのパートナー企業です。
業界を知り尽くしているからこそ大手の取引先企業、経験豊富なエンジニアに選ばれています。
-
正社員なのにフリーランスのような働き方

正社員の方でも希望を聞いたうえでプロジェクトをアサインさせていただいており、フリーランスのような働き方が可能。帰社日もありません。
プロジェクト終了後もすぐに次の案件をご紹介させていただきますのでご安心ください。
-
大手直取引の高額案件

案件のほとんどが大手SIerやエンドユーザーからの直取引のためエンジニアの皆様へに高く還元できています。
Ciscoをはじめ、Juniper、Azure、Linux、AWS等インフラに特化した常時300件以上の案件があります。
-
スキルアップ支援

不要なコストを削減し、その分エンジニアの方へのスキルアップ支援(ネットワーク機器貸出、合格時の受験費用支給など)や給与で還元しています。
受験費用例)CCNP,CCIE:6-20万円、JNCIS:3-4万円、AWS:1-3万円など
※業務に関連する一定の資格のみ。各種条件がありますので詳しくは担当者へにお尋ねください。
-
現給与を保証します!※

前職の給与保証しており、昨年度は100%の方が給与アップを実現。収入面の不安がある方でも安心して入社していただけます。
※適用にはインフラエンジニアの業務経験1年以上、等一定の条件がございます。
-
インセンティブ制度

ネットワーク機器の販売・レンタル事業等、売上に貢献いただいた方にはインセンティブをお支払いしています。
取引先企業とエンジニア側、双方にメリットがあり大変好評をいただいています。
-
社会保険・福利厚生

社員の方は、社会保険を完備。健康保険は業界内で最も評価の高い「関東ITソフトウェア健康保険組合」です。
さらに様々なサービスをお得に利用できるベネフィットステーションにも加入いただきます。
-
東証プライム上場企業グループ

ネプラスは東証プライム上場「株式会社夢真ビーネックスグループ」のグループ企業です。
安定した経営基盤とグループ間のスムーズな連携でコロナ禍でも安定した雇用を実現させています。
ネプラス株式会社に興味を持った方へ
ネプラス株式会社では、インフラエンジニアを募集しています。
年収をアップしたい!スキルアップしたい!大手の上流案件にチャレンジしたい!
オンライン面接も随時受付中。ぜひお気軽にご応募ください。

新着案件New Job
-
【高額年収】/【CCNA取得者歓迎】/ネットワークの構築/BIG-IP/東京都千代田区/【WEB面談可】/在宅ワーク/20代~30代の方活躍中
年収540万~540万円東京都千代田区(神保町駅) -
東京都中央区/【WEB面談可/インフラサーバ経験者/20~40代の方活躍中】/在宅ワーク
年収600万~600万円東京都中央区(小伝馬町駅) -
【高額年収】/インフラ構築支援/東京都港区/【WEB面談可/インフラサーバ経験者/20~40代の方活躍中】/在宅ワーク
年収960万~960万円東京都港区(新橋駅) -
ガバナンス推進、セキュリティ基盤支援/東京都港区/【WEB面談可】/在宅ワーク/20代~40代の方活躍中
年収780万~780万円東京都港区(新橋駅) -
カー用品販売会社の情報システム運用/東京都千代田区/【WEB面談可/インフラサーバ経験者/20~40代の方活躍中】/テレワーク
年収576万~576万円東京都千代田区(水道橋駅) -
ネットワーク構築、検証/東京都渋谷区/【WEB面談可】/テレワーク/20代~40代の方活躍中
年収540万~540万円東京都渋谷区(渋谷駅)