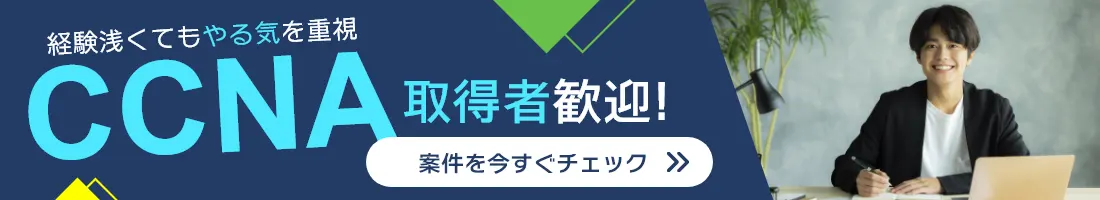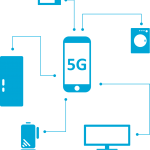NASとSANの違いとは?それぞれの特徴やクライアントから見た違いも解説

NASとSANを比較してわかる違いとは

ITについて学ぶ場合、基本的な知識としてストレージの知識も必要となります。また、近年ではネットワークストレージの「NAS」と「SAN」が注目を集めていることから、これらはストレージを学ぶ上で外せない知識だと言えるでしょう。
NASとSANはどちらもストレージですが、それぞれメリットやデメリットがあります。本記事ではストレージを知るうえで重要になるNASとSANを比較した違いなどを紹介していきます。
NASはファイルストレージ
NAS(Network Attached Storage)はもともとファイルサーバー専用に開発されたファイルストレージです。
1990年代のファイルサーバーは速度が低速で性能が低いという問題点があったため、ネットワークの転送速度が向上するにつれてNASの需要が高まり、企業用のファイルストレージとして一般的になっていきました。
また、現在では企業用としてだけでなく一般的に利用されるネットワーク接続のストレージとして認識されています。
SANはブロックストレージ
SAN(Storage Area Network)はデータへのブロックアクセスをサポートするブロックストレージです。一般的にはスイッチを経由してファブリックに接続するストレージです。
また、SANはさまざまな種類の異なるサーバーがアクセスできるようになっていることから、ストレージ専用ネットワークとも呼ばれています。複数のサーバーと複数対1で接続できることから、管理運用のコストなどを削減しています。
NASの特徴

ストレージについて学ぶ上で、NASとSANのそれぞれの特徴について理解を深めることは非常に重要です。それでは、NASは具体的にどのような特徴を持ったファイルストレージなのでしょうか。
ここではNASの特徴を紹介しますので、どのような特徴を持ったストレージなのか参考にしてみてください。
導入が容易で低コスト
NASはSANと比較すると、導入が容易でコストも低く導入することが可能です。NASを導入する場合はストレージを既存のLANに接続することになるため、非常に導入が簡単です。そのため、SANよりもはるかに容易かつ低コストでの導入が可能になります。
ただし、既存のLANに接続することからアクセス速度もLANに依存することになるため、通信速度を向上することは難しいでしょう。
異なるOS間での共有がしやすい
NASはSANと比較すると、異なるOS間でも共有しやすい傾向にあります。NASにはファイル共有に特化していることから、HTTP(Web)やCIFS(Windows)、NFS(UNIX)などの一般的なファイルアクセスプロトコルに対応しています。
そのため異なるOS間でもファイル共有することが可能となっており、非常に安定性が高くメンテナンスの手間もかからないなどのメリットがあります。
SANの特徴

ここまでNASの特徴について紹介してきましたが、NASと比較してSANはどのような特徴があるのでしょうか。
ここではSANの特徴をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
FC-SANとIP-SAN
SANには「FC-SAN」と「IP-SAN」という2種類があります。また、IP-SANはさらに「FCoE」と「iSCSI」という2種類に分かれています。
FC-SANとIP-SANには、それぞれネットワークや導入機器、プロトコルなどさまざまな違いがあり、さらにコスト面でも大きな違いがあります。ここではそれぞれ紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
FC-SAN
FC-SANはファイバチャネルネットワークを使用したSANです。FCは「Fiber Channel」を意味する言葉で、FC-SAはストレージとサーバーを接続する高速なネットワークとなっています。
しかしNASと比較して高い導入費用が掛かる点がネックになっており、FC-SANは高いパフォーマンスを発揮するのと同時に導入コストが高くなることから、企業の中にはSANの導入を控えるといったケースもありました。
FCoE
FCoE(Fibre Channel over Ethernet)とはSANとLANをイーサネットで統合するために考案されたIP-SANです。
規模の大きなシステムを構築する場合、FC-SANではLANだけでなくストレージ用にSANを構築する必要があるため、複雑なネットワーク構成になっていました。
しかしFCoEの場合はLANとFC-SANを統合できるため、消費電力やコストを削減できます。ただし、サーバーと同一ブロードキャストドメイン内でしか使えないというデメリットもあります。
iSCSI
iSCSI(Internet Small Computer System Interface)とはFCoEと同様にSANとLANを統合できるIP-SANです。FCoEとの違いは、iSCSIはSCSIをイーサネット上で使えるようにした規格であることです。
iSCSIは大規模システム構築に適したFCoEと比較して小規模なネットワーク構築に適していますが、異なるIPネットワーク間でやり取りできる一方でオーバーヘッドが増えるというデメリットがあります。
NASよりは高度な知識が必要
SANはNASと比較してより高度な知識が必要という特徴があります。先に紹介したDASの場合、ネットワークを経由してサーバーとストレージが接続されていないことから特に高度な知識は必要ありませんでした。
しかしSANの場合は既存のLANを使用するのではなく、専用のスイッチや専用のケーブルなどを利用して新しく導入する必要があるため、高度な専門知識が必要となります。
クライアントから見たNASとSANの比較

ここまでNASとSANと比較した場合のさまざまな特徴について紹介してきました。それでは、クライアントから見た場合には、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
ここでは最後に、クライアントから見た場合にNASとSANについてどのような違いがあるのかを紹介していきます。
ファイル単位かブロック単位か
クライアントから見た場合、NASはファイル単位、SANはブロック単位のように見えます。前述のとおり、NASはイーサネット、SANはファイバチャネルを使用して接続するという特徴がありますが、クライアントから見た場合には利用形態の違いが大きな特徴となっています。
利用形態によって分ける場合、NASはファイル単位を共有するストレージ、SANはロック単位を読み書きするストレージということになります。
NASはファイルサーバーに見える
クライアントから見た場合、NASはファイルサーバーのように見えます。単純にファイルを読み書きする場合、NASもSANも同様の仕組みを持っているものですが、実際に利用する場合、NASはファイルサーバーに見えます。
そのため、企業ではNASをファイルサーバーの代替品として利用するケースが多い傾向にあります。
SANはサーバーの内蔵ストレージに見える
クライアントから見た場合、SANは内蔵もしくは接続されたストレージのように見えます。つまり、クライアントからはサーバーのローカルディスクと同じように見えています。
SANではブロック単位で読み書きすることから、データベースに効率よくアクセスできるため、企業ではSAN対応のディスクシステムを基幹業務システムで利用するデータベースとして利用するケースが多い傾向にあります。
NASとSANを比較して違いや特徴を把握しよう

NASとSANはそれぞれ異なる特徴を持ったネットワークストレージです。そのため、ストレージについて学ぶ上では、NASやSANの違いについてもよく理解していく必要があります。
ぜひこの記事でご紹介したNASとSANを比較してわかる違いやNASとSANのそれぞれの特徴、クライアントから見たNASとSANの比較などを参考に、NASとSANの違いについて理解を深めてみてはいかがでしょうか。
FEnetを運営しているネプラス株式会社はサービス開始から10年以上
『エンジニアの生涯価値の向上』をミッションに掲げ、
多くのインフラエンジニア・ネットワークエンジニアの就業を支援してきました。

ネプラス株式会社はこんな会社です
秋葉原オフィスにはネプラス株式会社をはじめグループのIT企業が集結!
数多くのエンジニアが集まります。

-
インフラ業界に特化

ネットワーク・サーバー・データベース等、ITインフラ業界に特化。Cisco Systemsプレミアパートナーをはじめ各種ベンダーのパートナー企業です。
業界を知り尽くしているからこそ大手の取引先企業、経験豊富なエンジニアに選ばれています。
-
正社員なのにフリーランスのような働き方

正社員の方でも希望を聞いたうえでプロジェクトをアサインさせていただいており、フリーランスのような働き方が可能。帰社日もありません。
プロジェクト終了後もすぐに次の案件をご紹介させていただきますのでご安心ください。
-
大手直取引の高額案件

案件のほとんどが大手SIerやエンドユーザーからの直取引のためエンジニアの皆様へに高く還元できています。
Ciscoをはじめ、Juniper、Azure、Linux、AWS等インフラに特化した常時300件以上の案件があります。
-
スキルアップ支援

不要なコストを削減し、その分エンジニアの方へのスキルアップ支援(ネットワーク機器貸出、合格時の受験費用支給など)や給与で還元しています。
受験費用例)CCNP,CCIE:6-20万円、JNCIS:3-4万円、AWS:1-3万円など
※業務に関連する一定の資格のみ。各種条件がありますので詳しくは担当者へにお尋ねください。
-
現給与を保証します!※

前職の給与保証しており、昨年度は100%の方が給与アップを実現。収入面の不安がある方でも安心して入社していただけます。
※適用にはインフラエンジニアの業務経験1年以上、等一定の条件がございます。
-
インセンティブ制度

ネットワーク機器の販売・レンタル事業等、売上に貢献いただいた方にはインセンティブをお支払いしています。
取引先企業とエンジニア側、双方にメリットがあり大変好評をいただいています。
-
社会保険・福利厚生

社員の方は、社会保険を完備。健康保険は業界内で最も評価の高い「関東ITソフトウェア健康保険組合」です。
さらに様々なサービスをお得に利用できるベネフィットステーションにも加入いただきます。
-
東証プライム上場企業グループ

ネプラスは東証プライム上場「株式会社夢真ビーネックスグループ」のグループ企業です。
安定した経営基盤とグループ間のスムーズな連携でコロナ禍でも安定した雇用を実現させています。
ネプラス株式会社に興味を持った方へ
ネプラス株式会社では、インフラエンジニアを募集しています。
年収をアップしたい!スキルアップしたい!大手の上流案件にチャレンジしたい!
オンライン面接も随時受付中。ぜひお気軽にご応募ください。

新着案件New Job
-
【高額年収】/【CCNA取得者歓迎】/ネットワークの構築/BIG-IP/東京都千代田区/【WEB面談可】/在宅ワーク/20代~30代の方活躍中
年収540万~540万円東京都千代田区(神保町駅) -
東京都中央区/【WEB面談可/インフラサーバ経験者/20~40代の方活躍中】/在宅ワーク
年収600万~600万円東京都中央区(小伝馬町駅) -
【高額年収】/インフラ構築支援/東京都港区/【WEB面談可/インフラサーバ経験者/20~40代の方活躍中】/在宅ワーク
年収960万~960万円東京都港区(新橋駅) -
ガバナンス推進、セキュリティ基盤支援/東京都港区/【WEB面談可】/在宅ワーク/20代~40代の方活躍中
年収780万~780万円東京都港区(新橋駅) -
カー用品販売会社の情報システム運用/東京都千代田区/【WEB面談可/インフラサーバ経験者/20~40代の方活躍中】/テレワーク
年収576万~576万円東京都千代田区(水道橋駅) -
ネットワーク構築、検証/東京都渋谷区/【WEB面談可】/テレワーク/20代~40代の方活躍中
年収540万~540万円東京都渋谷区(渋谷駅)