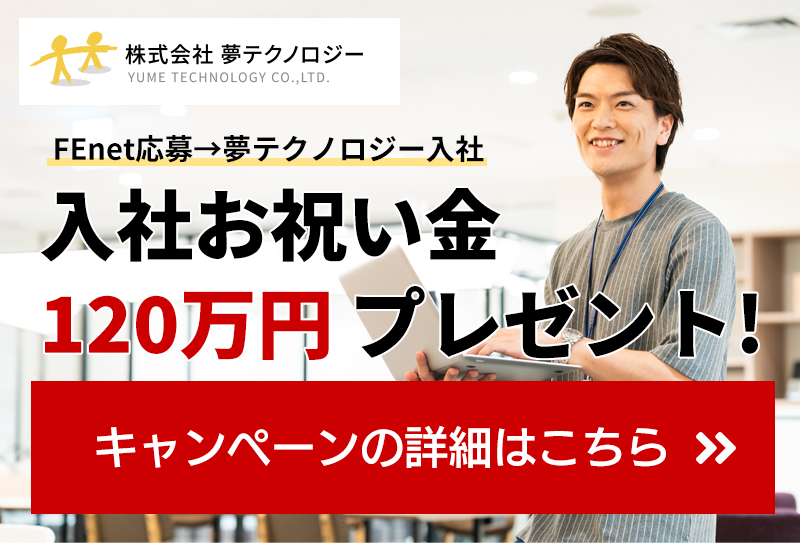目次
クローリングとはどのような作業のこと?

クローリングとはインターネット上にあるWebサイトをクローラーというプログラムで巡回することを意味します。
クローニングは主にインターネット上にある情報を収集する目的で行われるもので、Googleなどの検索エンジンでは新しく作成されたWebサイトの認識する目的で利用されています。
近年ではクローニングなどの技術によって、これまで手作業で行われていた情報収集作業が自動化され、効率化できるようになりました。
クローラーとは?
クローラーとはWebサイトを巡回するロボットです。
主に巡回先のWebサイト内にあるHTMLファイルなどを読み込み、検索のデータベースへ登録しています。クローラーはリンク情報をたどり、Webサイトがどのような構造になっているのか、どのような内容なのかを確認します。
そのため、新しく作成したWebサイトが早く検索エンジンに上がるようにしたい場合、クローラーが見つけやすいようにクローラビリティを高める必要があります。
クローリングとスクレイピングの違い

クローラーとはWebサイトを巡回することを指し、スクレイピングは情報を取得する技術を指す言葉です。
クローラーがWebサイトを巡回する目的は情報を集めることですが、実際に集めた情報から不要な情報を削り、重要な情報のみを取得できるようにしているのはスクレイピングです。
そのため、Webサイトから情報を収集したい場合には、Webサイトをクローリングし、収集した情報から特定の情報をスクレイピングすることになります。
転職者が理解しておきたいクローリングの仕組み3つ

クローリングの仕組みをご紹介します。
ネットワークエンジニアやシステムエンジニアなどIT業界への転職を検討している場合には、クローリングなどの技術についても把握しておくことが重要です。
ここでは転職者が理解しておきたいクローリングの仕組み3つをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1:クローリングされるときの手順
クローリングされるときの手順をご紹介します。
自社で新しくWebサイトを構築した場合など、早くクローリングされてインターネット検索に上がるようにしたいと考えます。それでは、クローリングはどのような手順で実施されているのでしょうか。
ここではクローリングされるときの手順をご紹介します。
HTMLの中にあるリンクを発見する
クローリングは巡回先であるWebサイトのHTML内にあるリンクを発見すると、発見した次のWebページへ進んでいくという方法になります。
そのため、インターネット上に点在しているWebサイトに張り巡らされている蜘蛛の網を渡り歩くように見えることから、クローリングはスパイダーと称されることもあります。
Webページを自動的に循環する
クローリングは自動的にWebページを巡回し、情報を収集していくことになります。
誰かが操作してクローリングを進めているのではなく、インターネット上に張り巡らされた網をクローラーは自動的に循環しています。そのため、Webサイトを運営している側はいつ情報収集されているのか知ることはできません。
2:1度訪れたサイトはクローリングされる
クローラーが1度巡回したWebサイトに関しては、リンクを辿らずにクローリングの対象となります。
クローラーがすでに存在を把握しているWebサイトに関しては、クローラーが通るための道ができている状態になります。そのため、一度でもクローラーがWebサイトへ訪れれば、検索エンジンに載るためのルートができあがると言えるでしょう。
3:情報収集の頻度は決まっていない
クローラーが情報収集をどの程度の頻度で実施しているのかは、特に決まっていません。
情報収集の頻度はシステムによる自動反映となっています。そのため、Webサイトを運営しているユーザー側には情報収集がいつ行われるのか知ることはできません。
ただし、「Google Search Console」などを利用すると、Googleのクローラーがいつ自社のWebサイトをクローリングしたのか知ることができます。
転職者がクローリングを活用すべき理由3つ

転職者がクローリングを活用すべき理由をご紹介します。これからIT業界へ転職しようと考えている方にも、クローリングは活用することができる非常に便利な技術です。
ここでは転職者がクローリングを活用すべき理由3つをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
1:業務効率を改善できる
クローリングを活用することにより、これまで手作業で行ってきたWebサイトからの情報収集作業の効率を改善することができます。
手作業でインターネット上の情報収集を行う場合、できる範囲が限られている上に膨大な時間がかかります。しかしクローリングによってプログラムに作業を任せることができれば、その間に人は他の作業を進めることができます。
また、クローリングは人が手作業で収集するわけではないため、ヒューマンエラーなどのリスクも軽減できます。
2:大量のデータの収集に役立つ
クローリングを活用することにより、自動的に膨大な量のデータを収集することができます。Webサイトにはさまざまな情報があるため、収集して分析を行うことでマーケティングやAI開発などのビジネスに役立てることができます。
そのため、クローリングを利用して短期間で大量のデータを収集し、集めたビッグデータをAI開発などの最先端分野の研究に役立てることも可能です。
3:SEO対策効果があるか確認するため
クローリングを活用することで、SEO対策効果があったかどうかを確認することができます。WebサイトがクローリングされることでWebサイトから情報収集が行われ、Google検索などの検索エンジンに反映されることになります。
そのため、SEO対策を実施した後でクローリングされた結果、以前よりも検索順位が上位表示になっていれば、SEO対策に効果があったことがわかります。
転職者が覚えるべきクローリングの構築方法4つ

転職者が覚えるべきクローリングの構築方法をご紹介します。クローリングがGoogle検索の情報収集用に用いられていることはご紹介しましたが、クローリングは自分で開発することも可能です。
ここでは転職者が覚えるべきクローリングの構築方法4つをご紹介しますので、IT企業への転職を検討している方はどのような方法で構築できるのか把握しておきましょう。
1:構築におすすめの言語
クローリングを構築するにはRubyやPythonなどのプログラミング言語がおすすめです。Rubyには効率的な開発をサポートするライブラリが用意されており、クローリングには「Nokogiri」というライブラリが便利です。
また、Pythonでクローリングを構築する場合は、「requests」と「Beautiful Soup」という2つのライブラリが一般的に利用されています。
2:クローリングに必要なファイル
クローリングを構築するにはサイトマップと呼ばれるXMLファイルとrobots.txtというファイルが必要です。
サイトマップはクローリングするURLが記載されているもので、このサイトマップを利用することで正確なクローリングが可能になります。また、サイトマップはrobots.txtで配置が表示されます。
robots.txtは、クローラーがどのサイトへアクセスすればよいのかわかるようにURLを記載したファイルです。
3:ツールの活用
プログラミングによってクローリングを構築しなくても、クローリングツールを使用する方法もあります。
自分でクローリングを構築するプログラミングスキルがない場合は、「Octoparse」や「Import.io」などのクローリングツールを利用するのがおすすめです。
どちらも無料プランが用意されているなど無料で利用することができるため、試しに利用してみると良いでしょう。
4:構築の手順
Pythonのrequestsを使ってクローラーを構築する手順をご紹介します。
requestsであれば、pipでインストールし、下記のようにコードを記述して実行するだけでクローリングが試せます。
import requests
url=”クローリングしたいサイトURL”
response=requests.get(url)
response.encoding=response.apparent_encoding
print(○○.text)
クローリングを行うときの注意点

クローリングは著作権法に触れるケースがあります。
Webサイトの中には情報収集を禁止しているものもあり、そういったサイトに対してクローリングしてしまい、情報を利用すると最悪の場合訴えられる可能性もあります。
また、クローリングはWebサイト負荷をかけることになるため、場合によってはサーバーダウンさせてしまう可能性もあります。
転職前にクローリングを覚えよう

クローリングを活用することで、自動的にインターネット上の情報を収集することができます。
ぜひこの記事でご紹介したクローリングの概要や仕組み、クローリングを活用すべき理由や構築方法などを参考に、クローリングについて理解を深めてみてはいかがでしょうか。
インフラエンジニア専門の転職サイト「FEnetインフラ」
FEnetインフラはサービス開始から10年以上『エンジニアの生涯価値の向上』をミッションに掲げ、多くのエンジニアの就業を支援してきました。
転職をお考えの方は気軽にご登録・ご相談ください。