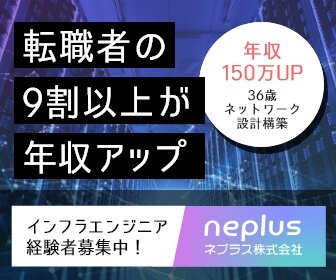ネットワーク設計の基本的な手順11個|構築・運用を安定させるポイントも紹介

ネットワーク設計とは?

ネットワーク設計とは、コンピューターやプリンターなどをLANケーブルや無線で繋いで利用できるような環境を構築することです。
企業でネットワーク設計を行う場合、データを保存するためにはサーバーが必要になるため、全社員でデータを共有するためにどのような構造が最適なのかを十分に検討する必要があります。
ネットワーク設計で押さえたいポイント
企業にとってのネットワークは、業務効率に直接影響を与える重要な部分となります。
しかし無計画にネットワーク設計を行うと、使いづらく設計者以外は理解できないようなネットワークになってしまうケースも多いです。
そのため、企業の目的に合った設計を行うことはもちろん、実際にパソコンを使ってネットワークを利用する社員にとって使いやすいネットワーク設計を行う必要があります。
ネットワーク設計におけるLANとWANの違いとは?

ネットワーク設計にはLANとWANの2種類があります。
LANは「ローカルエリアネットワーク」のことで、会社や家などの同じ地基地内に限定した範囲でのネットワークを指します。
一方、WANは「ワイドエリアネットワーク」を意味し、企業であれば本社と支店というように、広範囲でネットワークを接続することを指します。
LANでのネットワーク設計時の注意点
LANを使用したネットワーク設計を行う場合、有線LANを利用する方法と、無線LANを利用する方法の2種類があります。
LANは実際にLANケーブルを使用してネットワークに接続する方法ですが、無線LANの場合はワイヤレスで接続することになるため、そのままでは誰でもアクセス可能な状態になってしまいます。
そのため、セキュリティには十分気を付ける必要があります。
WANでのネットワーク設計時の注意点
WANでネットワーク設計を行う場合、個人では接続することができないため、通信事業者のサービスを導入して接続を行うことになります。
そのため、利用するサービスや接続形態などによって利用料金は異なります。
目的に合わせてしっかりと検討するようにしましょう。
ネットワーク設計の基本的な手順11個

ネットワーク設計を行う場合、企業の規模や社員数などによって接続するパソコンの台数は異なるため、企業に合わせてネットワークを構築する必要があります。
それでは、実際にネットワーク設計を行う場合、どのような手順で行えばよいのでしょうか。ここではネットワーク設計の基本的な手順11個をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1:現在の社員の人数の増減の予測を立てる
企業でネットワーク設計を行う場合、必要なパソコンやプリンターなどのノードの数に合わせて割り振るIPアドレス数を決定します。
IPアドレスは必要な数によってクラス分けを行うことになるため、将来的にどのくらい必要になるのかも予測することが重要になります。
そのため、現在の社員数だけでなく将来的にどのくらいの社員数になるのかまで予測して、余裕を持った設計を行いましょう。
2:ネットワークの拡張の想定
前述のとおり、ネットワーク設計では将来的にどのくらいの社員数になるか予測することが重要ですが、その際に将来的なネットワークの拡張性まで想定することが大切です。
現在は通信速度に問題が無くても、将来社員数が増えた場合、ネットワークを接続するノードが増えることによってパフォーマンスの低下を引き起こす可能性もあります。
また、割り振れるIPアドレスが枯渇して業務自体が停止するリスクがあります。
3:利用中のアプリケーションの確認
業務で必要になるアプリケーションを確認しましょう。
特に必要ではないアプリケーションを常に起動させているような状態では、ネットワークの遅延にも繋がります。
また、アプリケーションを際限なく利用しているとセキュリティ的なリスクを伴うケースもあるため、業務で必要なアプリケーションを調べて優先順位を決定しましょう。
4:今後どんなアプリケーションを導入するか
利用しているアプリケーションの確認を行ったら、実際にどのアプリケーションを導入するのかを決めましょう。
業務で必要になるアプリケーションは部署や職種などによっても異なります。
そのため、各部署の人数やアプリケーションの利用頻度などを確認し、どのアプリケーションをどの部署で使用するのか決めましょう。
5:ネットワーク改善に向けてのヒアリング
ネットワーク設計を行う場合、実際に利用する現場の社員の声を取り入れるのは非常に重要です。
すべての社員がパソコンやネットワークの利用に慣れているというわけではないため、ヒアリングをせずにネットワークを構築した場合、多くの社員にとって使いにくく不満が出るようなネットワークを構築してしまう可能性もあります。
また、どのアプリケーションを使用したいのか、現在のネットワークに問題がないかなどもヒアリングしましょう。
6:セキュリティを検討する
企業は顧客の個人情報などの非常に重要な情報を取り扱っているため、データを守るためにはネットワークにもアクセス制限を設ける必要があります。
また、外部からの攻撃を防ぐためもセキュリティ対策はもちろん、不正なアクセスがあった場合すぐにわかるような監視や検知ができるようにする必要があります。
さらに、実際に攻撃された場合でも業務に影響が出ないように、サーバーの冗長化などの対策を行うことも重要です。
7:物理的に必要な場所や電源の確保
ネットワークを構築する場合、サーバーを配置するためのサーバールームや電源などの確保が必要になります。
サーバーは常に稼働させておく必要があることから熱を放出するため、空調設備などがしっかりとした場所を用意しましょう。
また、停電などが発生した場合でもサーバーが止まらないように、電源が断たれた場合すぐに予備の電源に切り替わるような設備を整える必要があります。
8:ネットワークの接続形態を考える
ネットワーク設計を行う場合、ネットワークの接続形態(ネットワークトポロジー)を検討する必要があります。
ネットワークの接続形態にはさまざまな種類があるため、物理的、論知的両方の側面から最適な接続形態を検討することが重要です。
ネットワークの接続形態としては「ツリー型トポロジー」「スター型トポロジー」「フルメッシュ型トポロジー」「リング型トポロジー」「バス型トポロジー」があるため、それぞれの特徴をご紹介します。
ツリー型トポロジー
ツリー型トポロジーは階層ごとに接続しているネットワーク接続方法です。
1つ目の階層には1つのノード、2つ目の階層には2つのノードといった風にツリー型に接続を行います。
各階層に接続されているルートノードが故障すれば障害が発生しますが、それ以外の障害であれば他のノードへの影響は少ないです。
スター型トポロジー
スター型トポロジーは現在のLANケーブル接続での主流の接続方法です。
パソコンやプリンターなどのノードを1つの集約した集積装置に接続し、そこからルーターへ接続してインターネットにつなぐ接続方法になります。
スター型トポロジーは低コストでの運用が可能ですが、集積装置に障害が発生するとすべてのノードが接続できなくなるというデメリットがあります。
フルメッシュ型トポロジー
フルメッシュ型トポロジーとは、すべてのノードが接続されるようにネットワークを設計するものです。
そのため、たとえばルーターをフルメッシュ型トポロジーで接続した場合、一か所で通信障害が発生しても他のルーターに切り替えることができます。
このことから、フルメッシュ型トポロジーは耐障害性に優れているという特徴があります。
リング型トポロジー
リング型トポロジーは昔使われていた論理的トポロジーの1つです。
仮想的なリングを巡回しているトークンを使ってデータの送信を行うネットワーク接続方法で、現在では使用されていません。
バス型トポロジー
バス型トポロジーは1つの同軸ケーブルの両端に抵抗器を取り付け、パソコンやプリンターなどのノードを接続する方法です。
通信自体の安定性はあるものの、同軸ケーブルに通信障害が発生した場合にはどのノードも全く通信ができなくなるというデメリットがあります。
バス型トポロジーは古い接続方法となっており、現在の主流ではありません。
9:セキュリティの確保と利便性の向上
企業のネットワークは情報漏洩を防止するためのセキュリティを確保しつつ、実際に利用する社員にとっての利便性も高める必要があります。
そのため、誰でも自由にネットワークに接続できる状態にするのではなく、許可したユーザーはネットワークにアクセスできるようにし、USBの持ち込みはできないようにするなど、セキュリティを意識しつつネットワーク設計を行う必要があります。
10:ネットワークの冗長化
ネットワークの冗長化とは、障害発生時に予備のネットワークを配置し、運用を行うことです。
外部からのサイバー攻撃や障害発生時など、ネットワークに予期せぬトラブルが発生するケースはあります。
そういった場合に業務を全て停止するのではなく、ネットワークの冗長化を行うことで、業務に影響を与えないようにすることが重要です。
冗長化エリアについて
ネットワーク設計を行う場合はネットワークの冗長化についても検討しておく必要があります。
冗長化を行っておかなければ、障害発生時に業務を止めてしまう事になります。
また、冗長化エリアには「バックボーンエリア」「サーバーエリア」「ユーザーアクセスエリア」の3つがあります。
ここでは冗長化エリアについてそれぞれご紹介します。
バックボーンエリア
バックボーンエリアとは、一般的な通信が経由することになるメインのエリアのことです。
たとえば、インターネット接続エリアやデータサーバーエリア、ユーザーがアクセスするエリアなどがバックボーンエリアとなります。
多くの通信がバックボーンエリアを経由することになるため、バックボーンエリアの冗長性は非常に重要となります。
そのため、バックボーンエリアでは機器の内部構成と配置構成両方で冗長性を確保するようにしましょう。
サーバーエリア
サーバーエリアでは、機器の内部で冗長化しておくようにしましょう。
冗長化を行うことにより、万が一のトラブルでサーバー障害が発生した場合でも、業務を止めずに継続できるようになります。
ユーザーアクセスエリア
ユーザーアクセスエリアは特に冗長化を行う必要がないエリアです。
ただし、定期的にチェックを行い、不要なソフトウェアを削除したりメモリを解放するなどのメンテナンスを行う必要があります。
定期的なチェックによってパフォーマンスが落ちないようにしましょう。
11:管理者が運用しやすい自社に合ったネットワークを選ぶ
ネットワークは自社の条件にマッチしたものを選ぶようにしましょう。
また、管理者が運用しやすいようなネットワークを選ぶことが重要です。
高性能なネットワークを設計したとしても、会社の規模によってはどこまでのネットワークは不要であったり、管理者にとって使いにくい構成になっていては本末転倒です。
ここまでご紹介したさまざまな条件や種類などを参考に、条件に合ったネットワークを選択しましょう。
構築・運用をより安定・手軽にしてトラブルを軽減させるポイント3つ
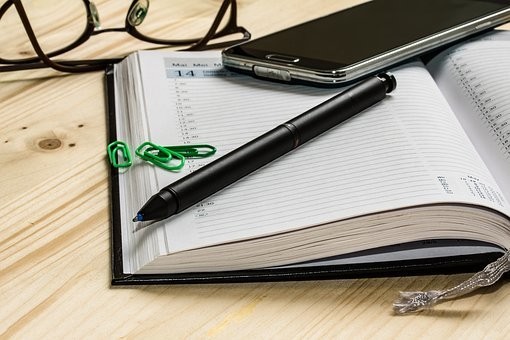
ネットワーク設計を行う場合、できるだけトラブルを発生させない構造にしたいと考えるのが普通です。
それでは、トラブルを軽減させるにはどのようなポイントを押さえればよいのでしょうか。
ここでは最後に、構築・運用をより安定・手軽にしてトラブルを軽減させるポイント3つをご紹介します。
1:ネットワークの構成図を書く
ネットワーク設計が終わると、次はいよいよ構築・運用の段階に入ってきます。
この構築・運用をよりスムーズにするために、設計段階で行っておきたいことがあります。
それは、分かりやすいネットワーク構成図を書くことです。
ネットワーク設計時には、ネットワーク構成図を作成しますが、この図には明確なルールが存在しません。
そのため、作成した人以外が見るとよく分からない図になっていることがあります。
そうなると、設計はもちろん、構築や運用段階で困ってしまいます。
たとえば機器同士の接続を分かりやすく明記することで、トラブルがあった際にも原因を特定しやすくなります。
2:データの分離
データを1か所で保存していた場合、万が一破損した時に取り返しがつきません。
そのためデータを分離し、バックアップを取っておくことが重要です。
また災害やウイルスの脅威にさらされた時でも、データを分離しておくことで被害を抑えられます。
複数に分離しても、大本となるデータベースサーバーで管理を行えば、負担はそれほど増大しません。
3:予備システム
ネットワークでトラブルが発生した場合、大きな被害になることも珍しくありません。
メインシステムとは別に予備システムがあれば、トラブルがあった際にすぐに切り替えることが出来ます。
また大きなダメージを与えないため、事業を継続できます。
ネットワーク設計の手順とポイントを理解して業務に活かそう

企業でネットワーク設計を行う場合、企業の規模や目的に合わせた設計を行う必要があります。
ぜひ本記事でご紹介したネットワーク設計の概要やネットワーク設計の基本的な手順、トラブルを軽減させるポイントなどを参考に、自社にマッチしたネットワーク設計を行って業務効率化を目指してみてはいかがでしょうか。
※削除してください
ポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイント
ネットワーク設計ネットワーク設計ネットワーク設計ネットワーク設計ネットワーク設計
ネプラス株式会社はサービス開始から10年以上
『エンジニアの生涯価値の向上』をミッションに掲げ、
多くのインフラエンジニア・ネットワークエンジニアの就業を支援してきました。

ネプラス株式会社はこんな会社です
秋葉原オフィスにはネプラス株式会社をはじめグループのIT企業が集結!
数多くのエンジニアが集まります。

-
インフラ業界に特化

ネットワーク・サーバー・データベース等、ITインフラ業界に特化。Cisco Systemsプレミアパートナーをはじめ各種ベンダーのパートナー企業です。
業界を知り尽くしているからこそ大手の取引先企業、経験豊富なエンジニアに選ばれています。
-
正社員なのにフリーランスのような働き方

正社員の方でも希望を聞いたうえでプロジェクトをアサインさせていただいており、フリーランスのような働き方が可能。帰社日もありません。
プロジェクト終了後もすぐに次の案件をご紹介させていただきますのでご安心ください。
-
大手直取引の高額案件

案件のほとんどが大手SIerやエンドユーザーからの直取引のためエンジニアの皆様へに高く還元できています。
Ciscoをはじめ、Juniper、Azure、Linux、AWS等インフラに特化した常時300件以上の案件があります。
-
スキルアップ支援

不要なコストを削減し、その分エンジニアの方へのスキルアップ支援(ネットワーク機器貸出、合格時の受験費用支給など)や給与で還元しています。
受験費用例)CCNP,CCIE:6-20万円、JNCIS:3-4万円、AWS:1-3万円など
※業務に関連する一定の資格のみ。各種条件がありますので詳しくは担当者へにお尋ねください。
-
現給与を保証します!※

前職の給与保証しており、昨年度は100%の方が給与アップを実現。収入面の不安がある方でも安心して入社していただけます。
※適用にはインフラエンジニアの業務経験1年以上、等一定の条件がございます。
-
インセンティブ制度

ネットワーク機器の販売・レンタル事業等、売上に貢献いただいた方にはインセンティブをお支払いしています。
取引先企業とエンジニア側、双方にメリットがあり大変好評をいただいています。
-
社会保険・福利厚生

社員の方は、社会保険を完備。健康保険は業界内で最も評価の高い「関東ITソフトウェア健康保険組合」です。
さらに様々なサービスをお得に利用できるベネフィットステーションにも加入いただきます。
-
東証プライム上場企業グループ

ネプラスは東証プライム上場「株式会社オープンアップグループ」のグループ企業です。
安定した経営基盤とグループ間のスムーズな連携でコロナ禍でも安定した雇用を実現させています。
ネプラス株式会社に興味を持った方へ
ネプラス株式会社では、インフラエンジニアを募集しています。
年収をアップしたい!スキルアップしたい!大手の上流案件にチャレンジしたい!
オンライン面接も随時受付中。ぜひお気軽にご応募ください。