目次
LPIC level3とは?

LPIC level3は、LPIC試験の上位試験です。LPIC試験とは「Linux技術者認定試験」の略で、最高レベルの技術力を持つ専門家であることが認定されるベンダー試験で、世界基準のIT資格として知られています。
LPI入門向けの資格である level1は未経験からインフラエンジニアを目指している方にお勧めの資格です。次の段階であるlevel2はLPI実務者向けの試験となります。そして、最終レベルであるlevel3では、十分な知識と実務経験が求められます。
level3はlevel1、2とは違い、独学での合格は難しいと考える人も多いですが、そのため、LPI公式の自習会が開催されてるほか、認定校も充実しています。
LPIC level3の前提
LinuxはUnix系のオペレーションシステムでその中でもLinuxディストリビューションはサーバーオベレーションシステムとして長年使われています。
日本国内だけではなく世界中でLinuxは利用されており、そのためLPIC level3は国際的に認められたベンダー試験となっています。LPIC level3を取得することで、Linuxを扱えるという技術力の裏付けになるだけではなく、高い割合のシェアを誇るLinuxの知識が得られるという点でもLPICを受験するメリットが得られるでしょう。
エンジニアとして活躍するだけではなく、Linuxの知識があれば、オフィスなどでのシステムのトラブルにわざわざ業者を呼ばなくても対応できます。認定を受けることで自身の市場価格を上げることに繋がるでしょう。
LPIC level3は、 level1、2に合格して初めて受験ができます。試験は300試験、303試験、304試験のいずれかに分かれています。各試験に合格することで、その分野のエキスパートエンジニアであると認定されます。
LPIC level3の試験3種類

LPIC level3は3つの試験に分かれています。試験は300試験、303試験、304試験と独立しており、いずれか1つに合格すれば、その試験内容分野のエキスパートとして認定されます。
LPIC level3は難易度が高く取得するためには最低100時間以上の学習期間が必要です。また、難易度が高いため、実務に携わりある程度の知識が必須となります。
Linuxは世界中にシェアをもつため、LPIC level3を取得することで世界的に通用する資格を得ることになります。海外での転職を考えている場合にも強い武器になるでしょう。
LPIC level3の試験内容1:300試験
300試験は混合環境でのシステムインテグレーションやトラブルに対処する知識が身に付きます。混合環境とは、Linux、Windows、UNIXが混在する環境のことです。また、Sambaなどを使ったシステムや認証サーバーの構築にも役立ちます。
LPIC level3のどの試験にも共通することですが、LPIC level3を取得することで、LinuxやUNIXのスペシャリストとして認定されます。LinuxやUNIXは世界的なシェアを持つことから、世界的な資格を有していることの証明になるほか、転職やフリーランスヘ転向にも大きな武器になります。
LPIC level3の試験内容2:303試験
303試験はセキュリティに考慮したシステム設計スキルとサーバー構築力があることを客観的に証明する認定試験です。
資格取得には、システム設計やサーバー構築の経験が必要となり、教科書を丸暗記するような学習方法では取得は難しいでしょう。
経験が必要となる303試験に向けての学習は、実務にも生かせる知識の再確認、再取得にも役立ちます。知識の再確認を行うことで、業務をスムーズに行うことができたり、対応できる仕事の幅が広がったりと、自分自身の市場価値を上げることにもつながります。
LPIC level3の試験内容3:304試験
LPIC level3、304試験は仮想化システムや高可用システムを構築するスキルを有していることを証明する資格試験です。
受験することでさまざまな技術力が身につくほか、仮想化システムや高可用システムの構築、保守、運用に必要なスキルを有しているという客観的な証明となるため、転職やキャリアアップにも有利な認定資格と言えます。
また、304はより実務的な内容が多い試験のため実務に役立てることができる、という点もメリットです。
LPIC level3資格の6つの特徴
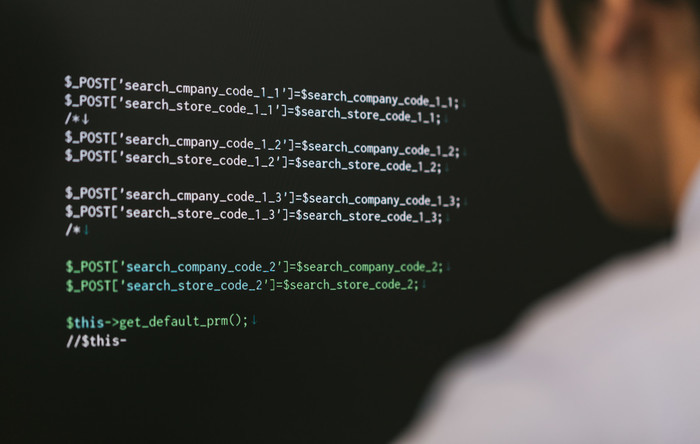
LIPCはLinux技術者に求められる技術を証明できる認定資格です。その中でもlevel3は「エキスパート」としての知識を認められる試験ですので、難易度が高いとされています。
しかし、この認定資格を取得することでIT業界での評価が高くなり、また、IT業界以外でも重用される価値の高い資格です。
LIPC level3の難易度はどのくらいか、学習期間はどのくらいを目安にすれば良いのか、合格点や各試験の試験範囲についてご紹介します。
LPIC level3資格の特徴1:難易度
LPIC level3の取得には十分な実務経験と知識が必要です。試験に合格するとその分野においてのエキスパートとして認定されることから、その分野での高度なスキルを保有するエンジニア向けの資格となっています。
300試験は出題範囲が広く、多くの主題とそこから枝分かれする細かい内容について学習するためにはたくさんの学習時間が必要になります。対策が難しい試験と言えるでしょう。
303試験では実務的な応用問題が多く出題されます。基礎問題が少なく、教科書の丸暗記では対処が難しくなります。実践的な応用問題や、実務で培った経験、知識が必要となる試験です。
304試験でも専門的な応用問題が出題されます。未経験者が合格するのは容易ではありません。304試験では、level1、2とは違いシンプルな問題が多く出題されるため、参考書や学習サイトで学習し、実際に実機にて検証しながら勉強するとより資格取得の近道になるでしょう。
LPIC level3資格の特徴2:勉強時間の目安
LPIC level3の学習時間は半年から1年程度が目安です。ただし、この時間はあくまで目安であり、もっと短い学習期間にて取得した方も多くいます。
LPIC level2の方が難しいと言う意見もあります。そのため、level2を取得した後、すぐにレベル3の勉強を集中的に行うと良いでしょう。
また、参考書や学習サイトを使って勉強するだけではなく、実機を使用し、問題集に出題されている問題を直接確認した方が良いです。直接手を動かすことで、理解力がかなり高まります。
LPIC level3資格の特徴3:合格点
LPICの合格点は500点です。満点がおおよそ800点のため、63%ほど正解すれば合格できると考えられます。
LPICでは20%ほどが難易度の高い問題と言われており、残りの80%の比較的シンプルな問題を正確に回答することで合格できるイメージです。
そのため、自信を持って回答できる問題をまず解いてから、自信のない問題に取り掛かったり、時間内にミスがないか何度も見直すと言った対策を取るようにしましょう。
LPIC level3資格の特徴4:合格率
合格率はLIPC公式では発表されていません。そのため、発表されている受験者数と合格者の数から推測するしかありません。
受験者数と合格者数から割り出すとLIPC level1〜3全ての合格者数を受験総数で割ると合格率は30%ほどと算出されると言われています。レベル毎の合格数の推測は難しいです。
2010年8月の段階ではLIPC 国内受験者は15万人以上、LIPC level3認定者は2700人以上と言われています。
LPIC level3資格の特徴5:試験の時間
LPIC level3の受験時間は90分で、出題数は60問です。しかし、試験後に簡単なアンケートがあり、試験問題を得のは実質85分となります。
時間的にも2、3回見直せる、余裕のある時間設定です。試験はコンピューターを用いたCBT方式です。キーボードの入力問題もあります。実技試験はありません。
問題は回答を見直したり、前の設問に戻ったり、見直したい問題にマークすることもできるので、まずは、自信のある問題を回答し、その後、自信のない問題に取り組むと良いでしょう。
試験を終了し、試験終了ボタンを押すとそのまま、合否がわかります。「合格おめでとうございます」の文字とともに取得点数が表示されます。
LPIC level3資格の特徴6:試験の範囲
LPIC level3の試験範囲は選択する試験によって異なります。
300試験は混在環境についてです。Windows、UNIX、Linuxシステムが混在するネットワーク環境で必要なスキルについて出題されます。Open LDAPの設定から、Sambaの基礎、共有設定、管理、Linux、Windowsに関する問題が試験範囲です。
303試験はセキュリティに考慮した設計などについてです。暗号化やホストセキュリティ、アクセル制御、ネットワークセキュリティについて出題されます。
304試験は仮想化や高可用性システムを構築するためのスキルについてです。仮想化、高可用クラスタ管理、高可用クラスタストレージについて出題されます。
LPIC level3のおすすめの勉強法3選

LIPC level3はLinuxを扱えるという技術を裏付ける証明書です。LIPCを取得することのは、キャリアアップ、年収アップにつながるため、取得するメリットが大きい資格となっています。
level3は難易度が高く、学習時間は半年から1年程度が目安です。しかし、適切な学習方法をすれば、その距離を最短にできる可能性もあります。
おすすめの学習方法についてご紹介します。
おすすめの勉強法1:学習サイトを使用する
インターネットの学習サイトを利用して学習できるメリットは、隙間時間を有効に活用できると言う点です。インターネット学習サイトに登録しておけば、電車の待ち時間や移動時間などを勉強時間に当てることができます。
また、インターネットの学習サイトでは、正解率から理解度を客観的に知ることができるシステムがあり、自分の弱点がわかります。模擬試験も実施されてるので、現段階での自分の実力を図ることもできるでしょう。
おすすめの学習サイト:LPICイージス
LPICイージスは LinuClevel1の対策のためのサイトです。Linux技術を効率的に学習できるよう体系的に解説されています。参考書とほぼ同様の内容で構成されています。
LinuCとは日本向けに特化した日本独自のLinuxの基本的な知識を証明する資格ですが、LIPCと受験内容に大きな違いはありません。
LPICイージスにて知識を取得し、Ping-tなどの問題集サイトにてアウトプットすることで知識が身に付きます。
おすすめの勉強法2:参考書の内容を理解する
参考書は内容を読むだけではなく掲載されている練習問題を解きながら理解を深めましょう。LPICは暗記をすれば合格可能とも言われます。そのため、参考書の内容をしっかりと読み込んで暗記しましょう。
試験対策だけならば暗記だけでも良いでしょう。しかし、スキルとして定着させたいのならば、実機を用いて手を動かしながら学習することでより理解が深まります。
おすすめの参考書:Linux教科書 LPICレベル3 300試験
いわゆる「あずき本」と呼ばれるLinuxの教科書です。300試験に対応しています。出題範囲が満遍なくわかりやすく解説されてます。一通り読んでから、豊富に掲載されている練習問題や巻末の模擬試験を利用して着実に合格力を鍛えることができます。
この教科書と問題練習をやりこめば合格点取得は難しくないでしょう。
そのほかにも、黒本と呼ばれる303試験・304試験に対応したLinuxの教科書もあります。
おすすめの勉強法3:テスト前に問題集を解く
参考書でインプットしたら、問題を解いてアウトプットしましょう。問題集は、Linux教科書に掲載された練習問題や、Ping-tなどで問題を繰り返し解いていきます。繰り返し回答することで自分の弱点がわかるので、弱点を補うような学習をします。
本番前には模擬試験を受験しましょう。模擬試験を1回から2回ランダムに受けて正解率が85%前後であれば、合格力がついていると判断できます。
おすすめの問題集:徹底攻略LPIC Level3 304教科書+問題集[Version 2.0]対応 徹底攻略シリーズ
徹底攻略LPIC Level3 304教科書+問題集[Version 2.0]対応 は通称黒本と呼ばれる参考書です。読みながら実際に環境の構築をします。
この本に掲載されている問題が試験に出るという情報があり、この本をしっかりと読み込み、掲載されている問題をやり込み、理解することで合格に近づくでしょう。
LPIC level3を取得して最高レベルの技術力を身につけよう!

Linuxは日本企業の約7割で導入されている高いシェアを誇るOSです。そのため、Linuxの高い技術を証明するLIPCは取得するメリットがとても大きい資格です。
難易度は高いですが、 level1を受験し、ステップアップしていくことでLinuxの知識が一通り身につくでしょう。 level3はエキスパートエンジニアのという証明ですので、キャリアアップにも役立ちます。LIPCは世界的にも通用するので、広い視野を持つことも可能です。
LIPC level3を取得して、高い技術力をアピールし、自分自身の市場価格を向上させましょう。
インフラエンジニア専門の転職サイト「FEnetインフラ」
FEnetインフラはサービス開始から10年以上『エンジニアの生涯価値の向上』をミッションに掲げ、多くのエンジニアの就業を支援してきました。
転職をお考えの方は気軽にご登録・ご相談ください。

















