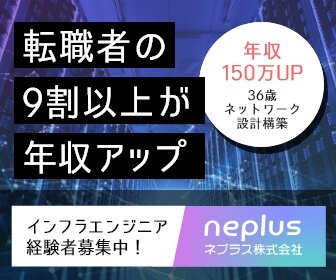ITILとは何か?5つの構成要素や導入がもたらす利点について解説

ITILとは

ITILとは、ITサービスマネジメントの成功事例をまとめたライブラリです。ITサービスマネジメントは、安定したITサービスを提供するための管理のことをいい、ITILは多くのITサービスマネジメントの考え方を整理したうえで提供してくれます。
ITILは、Information Technology Infrastructure Libraryの略語であり、ITサービスマネジメントのテンプレートの役割も果たします。
ITILを構成する5つの要素

ITILは「サービス・ストラテジ」、「サービス・デザイン」、「サービス・トランジション」、「サービス・オペレーション」、「継続的なサービス改善」という5つの構成要素から成り立っています。
ここでは、ITILの5つの構成要素について説明します。ITILがITサービスマネジメントの成功事例集であることを意識して、各要素の理解につなげていきましょう。各要素の構成は並列ですが、「継続的なサービス改善」はすべての要素にかかわります。
ITILを構成する要素1:サービス・トランジション
ITILのサービス・トランジションでは、移行の計画立案や変更管理などの項目を収集し整理します。ITILのサービス・トランジションで管理する項目は、ITサービスの立ち上げや旧サービスからの移行に関する項目です。
具体的には移行の計画立案や変更管理のほか、「サービス資産および構成管理」、「リリースおよび展開管理」、「サービスの妥当性確認およびテスト」、「変更の評価」、「ナレッジ管理」などを含みます。
ITILを構成する要素2:サービス・デザイン
ITILのサービス・デザインでは、ITサービスの設計や変更の際に必要となる情報を収集し、整理しています。具体的には、サービスカタログ管理や可用性管理、サービスレベル管理、デザインコーディネーション、情報セキュリティ管理、サプライヤー管理、キャパシティ管理、継続性管理などが挙げられます。
ITILのサービス・デザインを利用することで、品質や費用対効果などを考慮したうえでITサービスの設計や変更を遂行できます。
ITILを構成する要素3:サービス・オペレーション
ITILのサービス・オペレーションでは、ITサービスの運用に関する項目を整理しています。
具体的には、ITサービスの運用プロセスを構成する「インシデント管理」「イベント管理」「要求実現」「問題管理」「アクセス管理」といったプロセスに関する項目が整理されています。
そのほか、サービスデスクや技術管理、アプリケーション管理、IT運用管理といった機能に関する項目もサービス・オペレーションで整理されています。
ITILを構成する要素4:サービス・ストラテジ
ITILのサービス・ストラテジでは、財務管理や需要管理などの項目を整理し、ITサービスの戦略立案に役立てます。
サービス・ストラテジの市場分析を参考にビジネス領域を決定することができます。サービスを提供するための資源確保に必要な情報など、戦略的にビジネスを展開するために必要と考えられる情報は、サービス・ストラテジに収集し、整理しています。
サービス・ストラテジには、サービスポートフォリオ管理や事業関係管理なども含まれます。
ITILを構成する要素5:継続的なサービス改善
ITILではITサービスの継続的な改善についても整理しています。継続的なサービス改善では、「サービス・トランジション」、「サービス・オペレーション」、「サービス・デザイン」、「サービス・ストラテジ」でフローの見直しが必要になります。
継続してITサービスの見直しと改善に取り組み、サービス品質の向上にも寄与します。継続的なサービス改善は、特定の要素だけに行っても効果は薄く、ITサービス全体に対しPDCAサイクルを実施することで効果が得られます。
ITILの導入がもたらす利点5つ

ITサービスマネジメントの成功事例集であるITILを活用することで、企業にはどのようなメリットがもたらされるのでしょう。多くの企業がITILを導入しているという理由で倣って導入しても、期待したほどの効果を得られないということもあります。
ここでは、ITIL導入により期待できる利点を5つ紹介します。ITIL導入の利点を理解したうえで、効果的なITITLの活用を検討しましょう。
ITILの活用がもたらす利点1:利用者の満足度が上がる
ITILの活用により期待できる効果に、ITサービス品質の向上があります。ITサービス品質の向上は、そのまま利用者の満足につながる効果といえるでしょう。
ITILでは、ITサービス品質を可視化できるようになります。ITサービスに用いているサーバーやジョブ数などのほか、通常は数値管理しない管理項目についても数値で管理できるようになるため、改善目標も立てやすくなります。
ITILの活用がもたらす利点2:レジリエンス強化がはかれる
ITILの導入により、ITサービスを提供するシステムの安定した運用を行う目的でリスク管理の精度が高くなることも期待できます。
リスク管理を強化することで、ITサービスの問題発生を減少させられます。ITサービスに問題が発生することが減れば、サービスが安定し、ビジネスのレジリエンス強化をはかれることになります。
問題発生を減少させるためには、ITILを活用して問題管理を積極的に行っていく必要があります。
ITILの活用がもたらす利点3:ITサービス管理の意識が上がる
ITサービスの管理は、現場のエンジニアが担当することが多いことから、顧客目線よりも技術者目線になってしまうことも多く、顧客にとって不要な機能や技術が導入されていくことも少なくありません。
ITILを導入することで、ITサービスに対する問題や満足度も数値として可視化できることから、管理担当のエンジニアもITサービス管理に対する意識を顧客寄りに変えることが可能です。
ITILの活用がもたらす利点4:周囲環境への対応力が上がる
ITILを導入するメリットとして、ITサービスのライフサイクルマネジメント能力が向上することも挙げられます。ITサービスのライフサイクルマネジメントができることで、周囲環境の変化にも迅速に反応でき、対応が早くなると期待できます。
サービスを的確なタイミングで提供できるようになれば、市場の変化にも敏感に対応できるようになります。速いスピードで技術革新のなされているITサービスを、機を逃すことなく提供できます。
ITILの活用がもたらす利点5:コストが削減できる
ITILを導入することでITサービスマネジメント品質が向上すれば、ITサービスに無駄な技術や資源を投入することなく、費用をおさえても顧客が満足できるITサービスを展開できます。
直接的な費用作品というよりも、マネジメントに必要な評価を数値化し、誰が見ても明らかな形にすることで、現場や管理者といった立場の違いを超えて、ITサービスに有意義な機能や技術を判断でき、有効なコストのみを投入できます。
ITIL導入の際の注意点6つ

ITILを導入したら必ずITサービスマネジメントが成功に導かれるというものではありません。ITILはITサービスマネジメントの成功事例集ですが、間違った理解のもとでは、失敗を導いてしまうこともあります。
ここでは、ITILを導入するに際し、注意しておくべきポイントを6つ紹介します。成功事例をもとに成功案件につなげられるように、注意点を理解し、落とし穴となりうるリスクを意識しておきましょう。
ITIL導入の際の注意点1:インシデントが繰り返し発生していないか
ITILは成功事例集ですが、サービス・オペレーションでインシデント管理に関する項目も整理します。ITILで整理するインシデント管理は、その項目だけをどんなに眺めていても成功につなげることはできません。
同じあるいは類似のインシデント発生を防ぐためには、発生したインシデントの原因をつきとめ、対策を練ってはじめて予防につなげることができるからです。
同じインシデントが繰り返し発生しているようであれば、原因追求と対策のプロセスが十分ではないことになります。
ITIL導入の際の注意点2:3Pのバランスがとれているか
ITILを活用してITサービスマネジメントを成功に導くためには、「Process(プロセス)」「Person(人)」「Product(ツール)」という3Pのバランスに注目すると良いとされています。
プロセスでは、業務のやり方を向上させるための役割や責任について検討し、人に関してはメンバーのスキルアップをはかり、ITIL導入のためのツールとしてサポートツールの検討を行います。
ITIL導入の際の注意点3:ITILに対応していないツールで管理をしていないか
ITILを成功事例集として構築する際に、ITIL用のツールではなく、一般的な事務用アプリケーションであるExcelやWordを使って管理しようとしても、ITIL導入に期待するような効果が得られないことが多いと考えておきましょう。
一般的な事務用アプリケーションではITILに対応したシステムや項目がないので、担当者がうまく運用して補完しなければなりません。ITIL担当者の裁量に頼る部分となってしまい、担当者が変わるごとにITILの効果も変わってしまいます。
ITIL導入の際の注意点4:IT資産管理サービスデスクを分けていないか
ITILを使ってITサービスマネジメントを成功に導くためには、成功事例だけでなく、インシデントの対応も重要です。IT資産管理とサービスデスクが分けられていると、インシデント発生時の問題切り分けで、IT資産を把握するのに時間がかかってしまいます。
インシデント時に情報の共有を迅速に行うためにも、サービスデスクとIT資産管理は同じチームが担当するのがベストです。インシデントに素早く対応するために、サービスデスクでIT資産情報とインシデント情報を一元管理できるよう配慮しましょう。
ITIL導入の際の注意点5:継続的にPDCAサイクルができているか
ITILの構成要素の1つでもある「継続的なサービス改善」を実現させるためには、PDCAサイクルを実施し、適切な時期にITサービスの見直し・改善を行っていく必要があります。
ITサービスの運営状況や効果測定、課題などを整理して、改善すべき点を洗い出せるよう、PDCAサイクルが確実に実施できていることを確認しましょう。PDCAサイクルが実施されていないことを発見したら、運用自体の改善を考える必要があります。
ITIL導入の際の注意点6:利用者からの問い合わせを電話で受けていないか
ITILでのインシデント管理工数を削減するためには、インシデント受付者の作業を減らすという観点から、電話受付ではなくメール受付が望ましいとされています。
電話で受け付けると、内容を受付者がデータ化しなければならず、その工数がかかります。メールで受け付けの場合は、そのままデータとして取り込むか、カット&ペースト程度の工数でデータ化できます。
ITILではセルフサービスポータルやサービスカタログの活用を推奨しています。
ITIL関連のおすすめ資格5つ

ITILに関する資格は、ITIL®の所有者であるAXELOSによって実施されています。
ITILの資格としては、「Foundation(ファンデーション)」「Practitioner(プラクティショナ)」「Intermediate(インターミディエイト)」「Expert(エキスパート)」「Master(マスター)」の5種類があります。ここでは、ITILの5つの資格内容について紹介します。
ITIL関連のおすすめ資格1:Master資格
Masterを受験するためには、Expert資格を保有していることが条件で、最低でも5年間のITサービスマネジメントに携わっていることが前提となります。
受験に必須とされるトレーニングコースはなく、実務経験と論文で資格認定の審査が実施されます。Master資格はITILの最上位資格ですが、受験料を含め詳細は明らかにされていません。Expert資格を取得したうえで問い合わせる必要があります。
ITIL関連のおすすめ資格2:Intermediate資格
Intermediate資格を受験するためには、Foundation資格を保有していることが条件になります。認定教育コースの受講も必須とされており、Intermediate資格認定に必要な教育コースはライフサイクルとケイパビリティの専門分野で構成されています。
ケイパビリティの認定コースでは、役割やプロセスごとに4つのモジュールに分かれています。ケイパビリティ認定コースは日本語で受験可能です。
ITIL関連のおすすめ資格3:Practitioner資格
Practitioner資格は、Foundation資格とIntermediate資格の中間に位置付けられますが、Intermediate資格の必須資格とはなりません。
Practitioner資格を受験するためには、Foundation資格を保有していることが条件となり、Practitioner資格を認定されると、ITILの資格に必要な3クレジット(単位)を取得したことになります。
ITIL関連のおすすめ資格4:Foundation資格
Foundation資格はITILの資格を目指すうえで、最初に取得しなければならない資格です。Foundation資格の上位資格を受験するためには、Foundation資格を保有していることが条件になります。
Foundation資格取得のための勉強では、ITサービスマネジメントの基礎を学習することになります。Foundation資格を取得すると、ITIL資格の認定に用いられるクレジットを2単位取得できます。
ITIL関連のおすすめ資格5:Expert資格
Expert資格はITILの上位資格で、Foundation資格を保有しており、ITIL資格に必要なクレジットを17単位取得すれば必須コースであるMALCの受講と受験が可能になります。Expert資格に認定されるためには、専門分野の認定コースをバランスよく受講している必要があります。
Expert資格の認定には、必須となるMALCの受講を含め、22単位以上のクレジット取得が必要になります。Expert資格を認定されると、現場で活用できるだけのITIL能力がある証明になります。
ITILについて理解し導入してみましょう

ITILは即効で効果が出る仕組みではありませんが、時間をかけて着実にITサービスマネジメントを向上させていくことが期待できます。ITILの内容と効果を理解していないと、誤ったツールを導入してしまう危険性もあります。
ITILの運用をしっかりと理解し、きちんと効果をあげられるように検討したうえで、自社のITサービスマネジメントにとって適切なツールを導入しましょう。
ネプラス株式会社はサービス開始から10年以上
『エンジニアの生涯価値の向上』をミッションに掲げ、
多くのインフラエンジニア・ネットワークエンジニアの就業を支援してきました。

ネプラス株式会社はこんな会社です
秋葉原オフィスにはネプラス株式会社をはじめグループのIT企業が集結!
数多くのエンジニアが集まります。

-
インフラ業界に特化

ネットワーク・サーバー・データベース等、ITインフラ業界に特化。Cisco Systemsプレミアパートナーをはじめ各種ベンダーのパートナー企業です。
業界を知り尽くしているからこそ大手の取引先企業、経験豊富なエンジニアに選ばれています。
-
正社員なのにフリーランスのような働き方

正社員の方でも希望を聞いたうえでプロジェクトをアサインさせていただいており、フリーランスのような働き方が可能。帰社日もありません。
プロジェクト終了後もすぐに次の案件をご紹介させていただきますのでご安心ください。
-
大手直取引の高額案件

案件のほとんどが大手SIerやエンドユーザーからの直取引のためエンジニアの皆様へに高く還元できています。
Ciscoをはじめ、Juniper、Azure、Linux、AWS等インフラに特化した常時300件以上の案件があります。
-
スキルアップ支援

不要なコストを削減し、その分エンジニアの方へのスキルアップ支援(ネットワーク機器貸出、合格時の受験費用支給など)や給与で還元しています。
受験費用例)CCNP,CCIE:6-20万円、JNCIS:3-4万円、AWS:1-3万円など
※業務に関連する一定の資格のみ。各種条件がありますので詳しくは担当者へにお尋ねください。
-
現給与を保証します!※

前職の給与保証しており、昨年度は100%の方が給与アップを実現。収入面の不安がある方でも安心して入社していただけます。
※適用にはインフラエンジニアの業務経験1年以上、等一定の条件がございます。
-
インセンティブ制度

ネットワーク機器の販売・レンタル事業等、売上に貢献いただいた方にはインセンティブをお支払いしています。
取引先企業とエンジニア側、双方にメリットがあり大変好評をいただいています。
-
社会保険・福利厚生

社員の方は、社会保険を完備。健康保険は業界内で最も評価の高い「関東ITソフトウェア健康保険組合」です。
さらに様々なサービスをお得に利用できるベネフィットステーションにも加入いただきます。
-
東証プライム上場企業グループ

ネプラスは東証プライム上場「株式会社オープンアップグループ」のグループ企業です。
安定した経営基盤とグループ間のスムーズな連携でコロナ禍でも安定した雇用を実現させています。
ネプラス株式会社に興味を持った方へ
ネプラス株式会社では、インフラエンジニアを募集しています。
年収をアップしたい!スキルアップしたい!大手の上流案件にチャレンジしたい!
オンライン面接も随時受付中。ぜひお気軽にご応募ください。