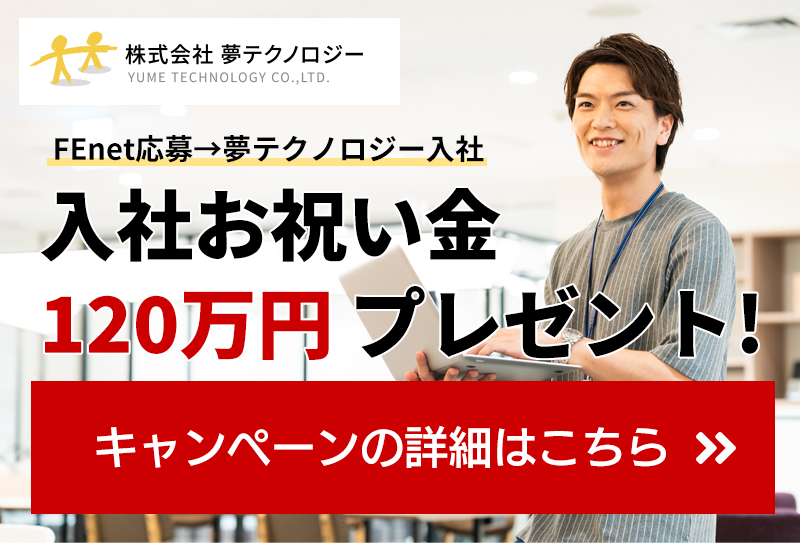目次
準委任契約とは?

民法第六百五十六条によると、準委任契約とは、発注者(委任者)側が法律行為ではない事務を受注者に依頼する委託契約のことです。
例えば、Web制作やシステム開発など、自社では制作・開発をすることが難しい業務については、専門の企業や個人に委託(外注)する場合などが挙げられます。
外注委託は、英語でアウトソーシングと言われています。
出典:民法第六百五十六条|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
委任契約との違い
委任契約と準委任契約の違いは、「法律行為を委託するかどうか」です。
委任契約は「法律行為を委託する契約」ですが、準委任契約は、事務処理などの「事実行為を委託する」契約になります。
では、法律行為とは何かというと、例えば代理人契約などが当てはまります。代理人が本人に代わって意思表示(法律行為)を行うので、代理人契約は委任契約ということになります。
これに対して、「事務処理などの事実行為」は講演やリサーチ業務、デザイン業務などの契約が該当します。一般的に委任契約に比べて準委任契約の方が、範囲が広い契約と言われています。
請負契約との違い
請負契約は、作業指示書などに沿って仕事を完成・納品することが基本となります。仕事を完成させることを目的としない準委任契約とは違い、請負契約では、受注者が1つの業務を完成させた時に、発注者がその仕事の結果に対し成果報酬を支払います。
そのため、品質保証に基づき、納品物を期限内に提出することが必要です。納品物が期限内に完成しないと、債務不履行となり契約違反となってしまうので、注意が必要です。
準委任契約の2つの種類
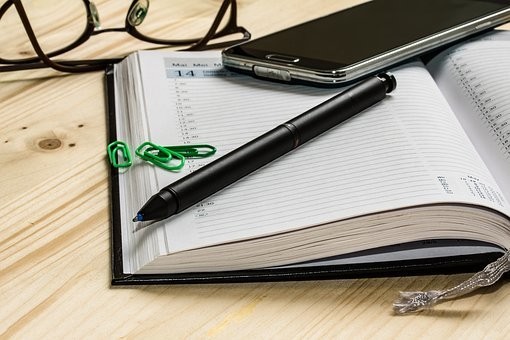
準委任契約には、成果報酬型と履行割合型の2種類があり、分けて定義されています。
契約の種類を知り、目的に併せて契約内容を選択するようにしましょう。契約によっては、中途解約や契約自体がなくなる可能性もあるため、しっかりと種類や内容を見ておくことが必要です。ここからは、準委任契約の2つの種類を解説していきます。
成果完成型
成果完成型とは、事務処理や調査・研究などの「成果」に対して発注者が報酬を支払う形を指します。契約した仕事を遂行した際に、発注者から報酬を受け取ります。検収方法は、前払い、毎月検収・毎月請求の2つから選択できるため、あらかじめ確認しておきましょう。
成果完成型は、成果物を納品することにより報酬が発生する契約となっています。
出典:民法644条 | e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
履行割合型
履行割合型とは事務処理や、調査・研究などの「労務」に対して発注者が報酬を支払う形を指します。契約した仕事において、労働時間や1日あたりの工数など業務量の進捗度に応じて、報酬を受け取る形式です。
履行割合型では、履行遅滞や報告義務を怠る・納品物の度重なるやり直しなどの違反行為がある場合は、契約不適合責任として契約解除に繋がる可能性があるため注意しましょう。
エンジニアが準委任契約を結ぶメリット3つ

準委任契約を結ぶメリットとは、どういったものがあるでしょうか。準委任契約の例には、クラウドサービスを活用したコンサルタント業務などがあります。準委任契約のメリットを知っておけば、業務をスムーズに遂行させることが可能です。
ここからは、準委任契約を結ぶことで得られるメリットを3つ紹介していきます。
1:業務を遂行することで報酬が得られる
準委任の契約を結ぶメリットとして、業務を遂行することで報酬を得られることがあげられます。発注者側と受注者側で契約期間や金額を決めた上で契約する形となるため、双方要件を伝えて、納得した条件で作業に取り組めます。
業務を遂行した地点で、受注者は報酬を得ることが可能です。
2:責任の重さを感じる必要がない
準委任契約は、決められた仕事を完了する義務が発生しません。そのため、設計や製作等の仕事を準委任契約で受注した場合に、納期までに完成品が仕上がらなかったとしても、受注側に責任が生じることはありません。
よって、役務による責任の重さを感じる必要がないという利点があります。
3:自由に作業ができる
準委任契約は、仕様変更について柔軟に対応しやすく、融通が利きやすい契約形態と言えます。作業場所や業務の進め方を役割分担しながら選べるため、自由度が高い点がメリットです。
準委任契約の場合、発注者側には納品物に対して作業指示をする権利がありません。
そのため、例えばシステム開発などの業務を受注したのが個人ではなく企業の場合、客先常駐がなく指揮命令・指揮命令権は受注者側が責任を持つ場合があります。その場合は、受注者側がスケジュール管理して業務を進めていくことになります。
エンジニアが準委任契約を結ぶデメリット2つ

エンジニアが準委任契約を結ぶデメリットは、2つあります。
無責任な契約を結んでしまうと、リスクが大きくなり、最悪の場合無報酬となることも考えられます。途中解約をすると、違約金の発生や損害賠償に繋がるため、注意が必要です。あらかじめデメリットを知っておくことで、業務間のトラブルや失敗を防ぐことが可能となります。
契約解除の可能性がある
準委任契約には、業務上の決まった成果物が定められないため、契約の内容が曖昧になりやすいという問題点があります。
発注者側と受注者側に契約内容のズレが生じると、ソフトウェア開発等業務の進行に支障がでるため、最悪の場合、契約解除や裁判・追加請求・追完請求となる可能性があります。
そのような事態を避けるため、契約前の打ち合わせでは、見積もり金額を口約束などではなく必ず契約書を交わすようにしましょう。
契約内容の認識がずれやすい
準委任契約には、仕事を完了させる義務が発生しないため、発注者と受注者の意識がズレる恐れがあります。不具合が重なることで、大きなズレが生じる可能性があるため、注意が必要です。契約時には、管理者や責任者等の体制図をしっかりと確認しておきましょう。
エンジニアが準委任契約をする際の注意点3つ

エンジニアが準委任契約する際には、3つのポイントがあります。契約内容の文言や条文、仕事量など事前に見ておくことで、金銭トラブルや人間関係のトラブルなどのリスクを防ぐことができます。契約時の見積り内容も、忘れずに確認しておきましょう。
ここからは、エンジニアが準委任契約をする際の3つの注意点を紹介していきます。
1:報酬を請求するタイミングを把握しておく
報酬を請求するタイミングは、契約内容によって変わります。
成果報酬型と履行割合型で請求するタイミングが違うこともありますし、検収日を基準として毎月報酬が振り込まれるのか、一括で振り込まれるのかによっても変わってきます。
請求するタイミングを間違えてしまうと、受注した企業に迷惑をかけてしまうことがあります。契約を交わすタイミングでしっかり支払条件等を確認しておきましょう。
2:作業時間や工数を管理する
作業時間や工数を管理しておくことも重要になります。ひとり単価あたりどれくらいの勤務時間・労務時間がかかるのか、作業工数が何工数程あるのかを確認しておきましょう。
また休日出勤の有無など勤怠管理だけでなく、交通費や収入印紙などの費用も把握しておきましょう。これらをしっかり把握しておかないと、受注金額に対して費用がかかりすぎてしまい、赤字になってしまうこともあります。
3:準委任契約か請負契約かを事前に明確にする
準委任契約では、下請法やスキル不足・クレームなどでトラブルとならないように注意が必要です。契約を交わす前には、事前に準委任契約か請負契約かを明確にしておきましょう。
請負契約の場合は、業務を完成させる責任が発生するため、契約書を交わす時に検収条件や請求書などについて確認しておく必要があります。有給休暇などの休みも、わかりやすく明記してもらうようにしましょう。
準委任契約を結ぶときは契約内容をしっかり確認しよう

準委任契約を結ぶ際に重要なことは、契約後の業務トラブルやお金のトラブルを防げるように発注側と受注側双方が納得する契約内容を結ぶことです。
個人事業主・フリーランスの方が準委任契約を結ぶ場合は、支払い方法や作業方法などに多くの注意事項があります。そのため、安全管理や安全配慮義務のみならず、労働基準法や労災・36協定などのその他ルールも把握しておくようにしてください。
委任契約書を結ぶときには、契約内容をしっかりと確認するようにしましょう。
インフラエンジニア専門の転職サイト「FEnetインフラ」
FEnetインフラはサービス開始から10年以上『エンジニアの生涯価値の向上』をミッションに掲げ、多くのエンジニアの就業を支援してきました。
転職をお考えの方は気軽にご登録・ご相談ください。